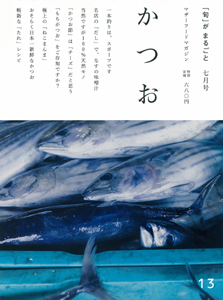闇の狩人(上)
仮眠から目ざめた谷川弥太郎は、小屋の台所に置いた戸棚の中へ手を入れ、なにやら、皿のものを取り出した。
しんしんと凍りつくような寒夜であった。
いつも食事をする飯屋[釘ぬき屋]から買って来た煮魚を、たっぷりかけた煮汁と共に深目の皿に入れたのを、昨夜から戸棚へ入れ放しにしておいたものである。
煮魚は汁と共に凍りつき煮こごりになっている。
弥太郎は、これが好物である。
一度、食べ忘れた魚がこうなっているのを口にしてからの事だ。
冷たい煮こごりに、冷たい酒で、弥太郎は、この日、二度目の食事を終えた。
闇の狩人(上)【煮魚の煮こごり】
料理:野崎洋光
材料:二人分
穴子の開き(1枚)生姜(15g)一番出汁(200㏄)
酒(100㏄)水(100㏄)醤油(50㏄)砂糖(20g)
みりん(50㏄)粉ゼラチン(8g)
主役の穴子は見るからに油がのり肉厚、先ずは一手間晒を被せる、その上に湯をかけ湯通し、余計な油や臭みを取る。
皮が反ってきたら、冷水にさらす。
包丁の背で皮のぬめりを軽くこそげるように取る、さらに水の中に入れ洗う。
主役の穴子は美しく磨かれた、大きさに整える。
鍋に一番出汁、酒、水、醤油、味醂、砂糖を入れ、火にかける、そこに穴子を入れ、沸騰したら弱火で15分煮る。
針生姜をつくる、粉ゼラチンを水で溶く、ゼラチンを鍋に入れ2分ほど煮、針生姜を入れて火を止める。
煮込んだ穴子を型に入れ、穴子に煮汁をかけ半分ほど浸す。
凍り水で冷やし、残りの煮汁も同様に冷やす、少し固まってきたら、さらに残りの煮汁を入れる。
後はじっくり冷蔵庫で一時間ほど冷やして完成。
現代では谷川弥太郎のように、凍りつくような寒夜を待たずして煮こごりが出来る。