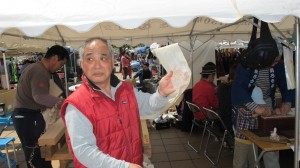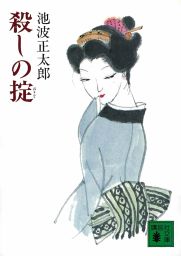信濃川の大河津分水路が出来る以前、寺泊では鰯が大漁に揚がったと聞きました。
大河津分水路が完成してからは新信濃川と言われた分水路から流れる土砂などで不漁が続き当時の面影すら無い浜に成った。
そんな寺泊の漁師のカミサン連中の保存食でも有った【鰯の塩漬け】を20年ほど作っては居ませんが、思い出して書いてみました。
勿論、当時は冷蔵庫など無い時代の物ですからその辺りをご考慮下さい。
【鰯の塩漬け】
料理:坂西美津雄
材料:活きの良い鰯(漬けたい分量)塩(応分量)
鰯は頭だけ落とし、腸などはその侭にべた塩をして重石をして漬ける。
3日程すると漬け汁があがってきます。
汁があがってきましたら本漬け、全ての汁はすて、新たに塩に漬け直します。
重しは必要有りませんが、漬け樽には蓋をして、涼しい冷暗所に保管下さい。
お盆が過ぎた頃には美味しい【鰯の塩漬け】が頂けます。
又、その鰯をオリーブオイルに浸ける事でアンチョビ風に頂く事も可能。
煮汁をキムチ漬けに使う朝鮮料理屋もあります。
注:鰯は必ず活きが良くヌタでも喰える物を使う。見て判断出来ない方は魚屋さんにヌタで食えるかと尋ねて求めるのも良いかと。
下記ウィキペディア大河津分水路
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%B2%B3%E6%B4%A5%E5%88%86%E6%B0%B4
椀の中の一汁一菜
【鰯のつみいれ汁】
料理:坂西美津雄
材料:二人分
鰯(2匹)昆布出汁(300㏄)越後味噌(適量)葱白い部分(60㎝×2)小麦粉(適量)塩(少々)生姜汁(少々)粉山椒(少々)
葱は開いて、白髪に切り水に放つ。
鰯は頭を落とし、手開きで中骨を抜き取り、包丁で叩き細かくする。
細かくなったら擂鉢に入れ、小麦粉を鰯の三分の一量、塩少々と生姜汁を入れ、よく混ぜて擂り上げる。
団子状に摘みとったたつみれを沸騰した鍋に落とし入れ、浮き上がるのを目安に掬い上げる。
出汁に好みの分量の味噌を溶きつみれを入れる。
沸騰したら火を落とし、椀に盛り、白髪葱をのせる。
粉山椒をふりいれ、頂く。
追伸
日本海で捕れる鰯は今が旬、大河津分水路の出来る前、寺泊の浜では鰯が大漁でした。
漁師のカァチャン連中は手にバケツを持って、売り物に成らない鰯を持ち帰り漬けたそうです。
私のバツ一の相方は寺泊の漁師の娘で、この母親や姉の漬けた塩鰯が最高に美味かった記憶が今でも残っています。
寺泊の鰯は糠を使わず塩だけで漬けまし。
この時期漬ければ秋には食い頃…♬
この鰯とだけは別れたくたく無かったなぁ
いひひ・・
5:40 2014/05/07
鬼平犯科帳5【乞食坊主】
鬼より怖く、仏のごとく優しい、火付盗賊改方長官、長谷川平蔵宣以。
この鬼平犯科帳【乞食坊主】では、平蔵の同門だった剣士で弟分の井関録之助が現れる。
録之助は、盗賊の密談を聞いたため命を狙われていた。
そしてこの事件をきっかけに、録之助も密偵に加わることに…。
乞食坊主に扮した録之助が、托鉢帰りに立ち寄った茶店で食べたのが【菜飯】である。
翌々日の昼前から、乞食坊主は、白金通りの両側を托鉢して歩いた。
この道はまっすぐに目黒不動へ通じ、江戸からの参詣道となっているだけに、町家もあるし、茶店も多い。
托鉢のついでに、坊主は目黒不動へ行き、菜飯と田楽で腹をみたしてから、あの小屋への帰途についた。
【菜飯】
料理:野崎洋光
材料:二人分
大根の葉(適量)米(2合)薄口醤油(30㏄)酒(30㏄)塩
米は研がずに優しく洗い、水を切り15分ほど置く。
よく洗った大根の葉を細かくきざみ、塩揉みして15分ほどおく。
15分経過したら余分な塩を洗い流し、水に晒す。
その後しっかりと水気を切る。
水気を切った米を土鍋に入れ、水300㏄、薄口醤油30㏄、酒30㏄を加えて炊く。
ご飯が炊きあがる間際に大根の葉を入れて10分ほど蒸らす。

殺しの掟【梅雨の湯豆腐】(講談社文庫)
彦次郎は盗賊、御座松の孫八の元で盗賊をしていたが、孫八を殺して逃げ、仕掛人となった。
そんな彦次郎の元へ二つの仕事が舞い込んだ。
仕掛ける相手は、大工の万吉と辻屋半右衛門の女房お照。
どちらも引き受け、探りを入れた、すると万吉は殺した孫八の甥でかつての盗人仲間。
さらにお照は孫八の一人娘だった。
なにやら裏がありそうだ?。
小料理屋で口の固い二人の男が闇の談合。
それは勿論…。
ここは、浅草今戸橋に近い三好屋という小体な料理屋で、蜆汁が売り物である。
近くに玉屋といって、これも蜆汁を名物にしている大きな料亭があるけれども、市兵衛に言わせると、「三好屋のほうが、ずっとうまい」のだそうな。
遠い赤坂から、こんなところまで、蜆汁が好きな市兵衛はよく足をはこんで来るらしい。
もう八ツ(午後二時)をすぎていたが、「いっしょに蜆飯を食おうよ」という市兵衛のさそいに、彦次郎はうすく笑ってかぶりをふり、「それじゃあ、これで」と腰をうかせた。
「そうかい。むりに引きとめはしねえよ。それで、いつごろまでにやっておくんなさるね?」「急ぐなら、おことわり申してえので……」「いやなに、いいとも。まかせるよ、まかせるよ」この仕事がすんだなら、残りの三十両が手に入るので、彦次郎は合わせて六十両で引きうけたことになる。
しかし、赤大黒の市兵衛は、略同額の金を依頼主からとり、自分のふところへ入れてしまったにちがいあるまい。
市兵衛がたのみ、彦次郎が引きうけた仕事というのは、〔殺し〕であった。
江戸へ住みついて十年になる彦次郎だが、この間、市兵衛からたのまれて殺しをしたのは五件ほどだったろうか…。
【蜆飯】と【蜆汁】
料理:田村隆
材料:二人分
蜆(1K)水(1L)塩水(水1L+塩10g)昆布(5g)
蜆は一時間ほど塩水に浸け砂抜きをする。
昆布を入れた水に洗った蜆を入れ火にかける。
蜆は開きだしたら火を止め蓋をする。
(余熱で蜆を開かせる)
煮汁を布巾で濾す。
【蜆飯】
米(1カップ)煮汁(200㏄)薄口醤油(小さじ1)蜆のむき身(60g)浅葱(10g)
煮汁、薄口醤油を入れ米を炊く。
ご飯が炊けたら蜆のむき身を入れ蓋をする。
茶碗に盛りつけた蜆ご飯に刻んだ浅葱を添える。
【蜆汁】
煮汁(400㏄)信州味噌(35g)蜆(250g)
煮汁に蜆を戻し、味噌を溶く。
沸騰したら火を止め椀に盛る。
鬼平犯科帳19【逃げた妻】(文春文庫)
木村忠吾の飲み仲間、浪人藤田彦七へ二年前に逃げた妻おりつから、助けを求める手紙が届いた。
藤田はすでに後添いをもらい、おりつの娘と三人で暮らしていた。
おりつを助けたい、でも今の生活を捨てる訳には……。
事を聞いた平蔵は、不穏な気配を感じ取った。
そこで、おりつが藤田と落ち合う前日、周辺を歩いてみると、昔、取り逃がした盗賊が……。
平蔵は茶店に入り辺りの事を覗う事に…。
木村忠吾が藤田彦七と会った翌日の昼下がりに……。
盗賊改方長官長谷川平蔵が大塚中町の通りを北へ歩む姿を見出すことができる。
今日の平蔵は、細川同心を従えてはいず、例によって着ながしの浪人姿で塗笠をかぶり、ゆっくりした足取りで、波切不動堂の前まで来た。
今日は風も絶え、雲一つなく晴れわたり、気温も上がったようだ。
波切不動堂の別当は、日蓮宗の通玄院だが、境内は、まことに狭い。
通りに面した空地の正面に茅ぶき屋根の茶店が一つあり、その左手に鳥居が見える。
藤田彦七の逃げた妻が、鳥居前の茶店、と書いてよこしたのは、この茶店であろう。
鳥居を潜って石段をあがると、黒塀の小さな門。
その門の向こうに本堂がある。
「ゆるせ」平蔵は茶店へ入り、あたりを見まわした。
変哲もない茶店である。
荷馬を外に繋いだ中年の馬方が一人、土間の腰掛で酒をのんでいた。
平蔵は茶店の老婆に酒をたのみ、塗笠をぬぎ、馬方から少しはなれた腰掛にかけた。
老婆が、ぶつ切りにした蒟蒻の煮たのを小鉢に入れ、酒と共に運んできた。
唐辛子を振りかけた、この蒟蒻がなかなかの味で、「うまい」おもわず平蔵が口に出し、竈の傍らにいる老婆へうなずいて見せると、老婆は、さもうれしげに笑った。
皺は深いが、いかにも人の善さそうな老婆だ。
【蒟蒻の煮しめ】
料理:田村隆
材料:二人分
蒟蒻(1枚)濃口醤油(大さじ半分+半分)砂糖(大さじ半分)出汁(200㏄)油(大さじ半分)赤唐辛子(半分)七味唐辛子(適量)
さっと湯通しした蒟蒻は両面を、すりこ木で軽く叩く。
両面を斜めから細かい包丁目を入れる。
コップを使い不揃いに切る。
フライパンに油を入れ炒める。
炒めて水分を飛ばす。
赤唐辛子を入れさらに炒める。
蒟蒻に水分が飛んだら、出汁、砂糖、濃口醤油を加え一煮立。
煮立ったら落し蓋をして中火でじっくり煮つめる、5分ほどしたら火を止め冷ます。
そして又火にかけ冷ます、この動作を3回繰り返す。
最後に醤油を加え、味を調える。
鬼平犯科帳9【白い粉】(文春文庫)
長谷川平蔵の家で料理番をしている勘助。
ここ数日味付けが妙である。
実は勘助博打で借金を造り、女房を連れ去られていた。
そして付きまとう男達から、金を返せぬのならと差し出された、白い粉。
つまり、平蔵の料理に毒を盛れと……。
勘助は悩みつつも夕餉の膳の吸い物へ白い粉を落とし込む。
腕ある男の得意料理、だがこの日の味はちっと違う。
上方でいう〔あぶらめ〕という魚。
関東では鮎並と言うし、江戸へ入る小さなのを〔クジメ〕ともよぶ。
長谷川平蔵は若いころから、この鮎並が大好物であった。
鮎並は細長い姿をしてい、緑褐色の肌に斑文が浮いているし、鮎のような姿ながら、あまり美しいとはいえぬ。
平蔵はこれを辛目に煮つけたものが、好きであった。
その日鮎並の煮つけが、夕餉の膳にのぼった。
「や、これは……」たのしげに箸を取って一口。
傍らにいた妻女の久栄は、さだめし、夫・平蔵の口から、「うまい!!」の一言が洩れるとおもっていたのだが、平蔵は小首をかしげ、もう一口。
「いかがなされました?」久栄の問いにはこたえず、平蔵は鯨骨の吸い物に口をつけて、「妙な……」と、つぶやいたものである。
「妙な?」「勘助のことよ」「勘助が、どうぞいたしましたか?」勘助は半年前から、長谷川家ではたらいている料理人なのである。
〔中略〕
「このごろ、勘助はどうかしている。ところに何ぞ、屈託があると見える」
【鮎並の煮つけ】
料理:田村隆
材料:二人分
鮎並(70g×2切れ)濃口醤油(50㏄)酒(50㏄)みりん(50㏄)砂糖(15g)鰹出汁(50㏄)くず粉(適量)木の芽(適量)
鮎並は三枚におろして、丁寧に骨抜きをする。
小骨が多いため骨切りをする。
骨切りをした中まで刷毛でくず粉を丁寧に付ける。
〔身の中に使った美味さを逃がさない一工夫〕
鍋に鰹出汁、酒、味醂、濃口醤油、砂糖を入れる。
一煮立ちしたら皮を下にして鮎並を入れる。
再び煮立ったら落し蓋をして3~4分煮る。
落し蓋をして3~4分煮たら一度火を止めて冷ます。
再び火を点け汁をかけながら味をしみこませる。
煮て冷ます、煮て冷ますの繰り返し。
鮎並の煮上がりは美味そうな黄金色に、小鉢に盛り木の芽を添える。
【真田太平記八】池波正太郎(新潮文庫)
天正10年。
武田勝頼、最後の砦[高遠城]。
城を守る足軽向井佐平治は、お紅に出会った。
お紅は、真田昌幸配下の忍び[草の者]。
城を脱した佐平治は、お紅と信州真田へ向かい、別所温泉で昌幸の次男源次郎信繁[幸村]に出会った……。
戦乱の山田舎、夕餉は忍びの者達にとって僅かな安らぎ。
その日の夕暮れになり、下久我の忍び宿の屋根裏の部屋で眠っていたお紅から合図があったので、権左が隠し梯子を下ろした。
すでに奥の部屋から奥村弥五平衛も起き出ている。
階下へ降りて来たお紅は、弥五平衛と共に夕餉の膳についた。
権左が支度した熱い粟飯である。
この粟飯は、権左が得意とするもので、干し柿と干し大根が刻みこまれていた。
「よう、眠れたか、弥五どの」「さて……」苦笑を浮かべた弥五平衛の瞼が、わずかに腫れている。
お紅も同様であった。
「やはりな……」「そちらも?」「うむ……」意味ありげな二人の遣り取りを権左が見つめている。
今夜の忍び宿には、三人きりであった。
【干し柿と干し大根を刻み込んだ熱い粟飯】
料理:田村隆
材料:二人分
もち粟(70g)玄米(2合)水(520㏄)切干大根(乾燥20g)干し柿(35g)酒(200㏄)味醂(40㏄)濃口醤油(40㏄)砂糖(10g)赤唐辛子(1本)昆布(15g)
先ずは玄米を洗う、研ぐと言うより優しく洗う。
洗った玄米は6時間以上水に浸ける。
もち粟は一晩水に浸ける。
玄米は浸けて置いた水事釜に入れ、もち粟は水切りしてから合わせ炊く。
切干大根は一晩水に浸け、戻して茹でておく。
切干大根に茹でた昆布を千切りにして入れる。
煮切った酒と味醂・砂糖・濃口醤油・赤唐辛子を入れ、一晩浸けこむ。
干し柿は種を除き1センチ角に切る。
浸けこんだ切干大根と昆布は水を切り細かく刻む。
炊けたもち粟に入った玄米に入れよく混ぜる。
茶碗に盛ったら刻んだ干し柿をのせる。